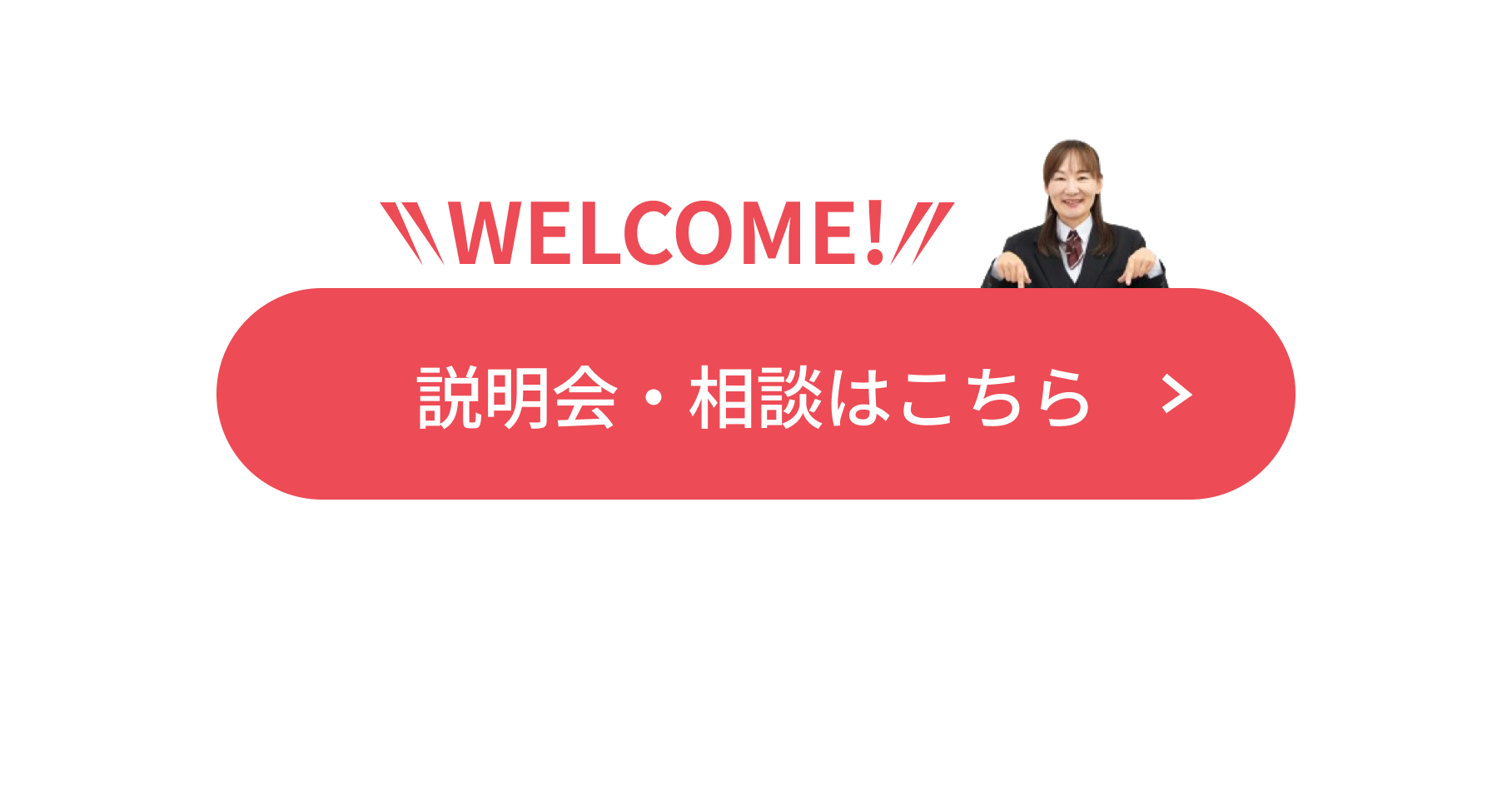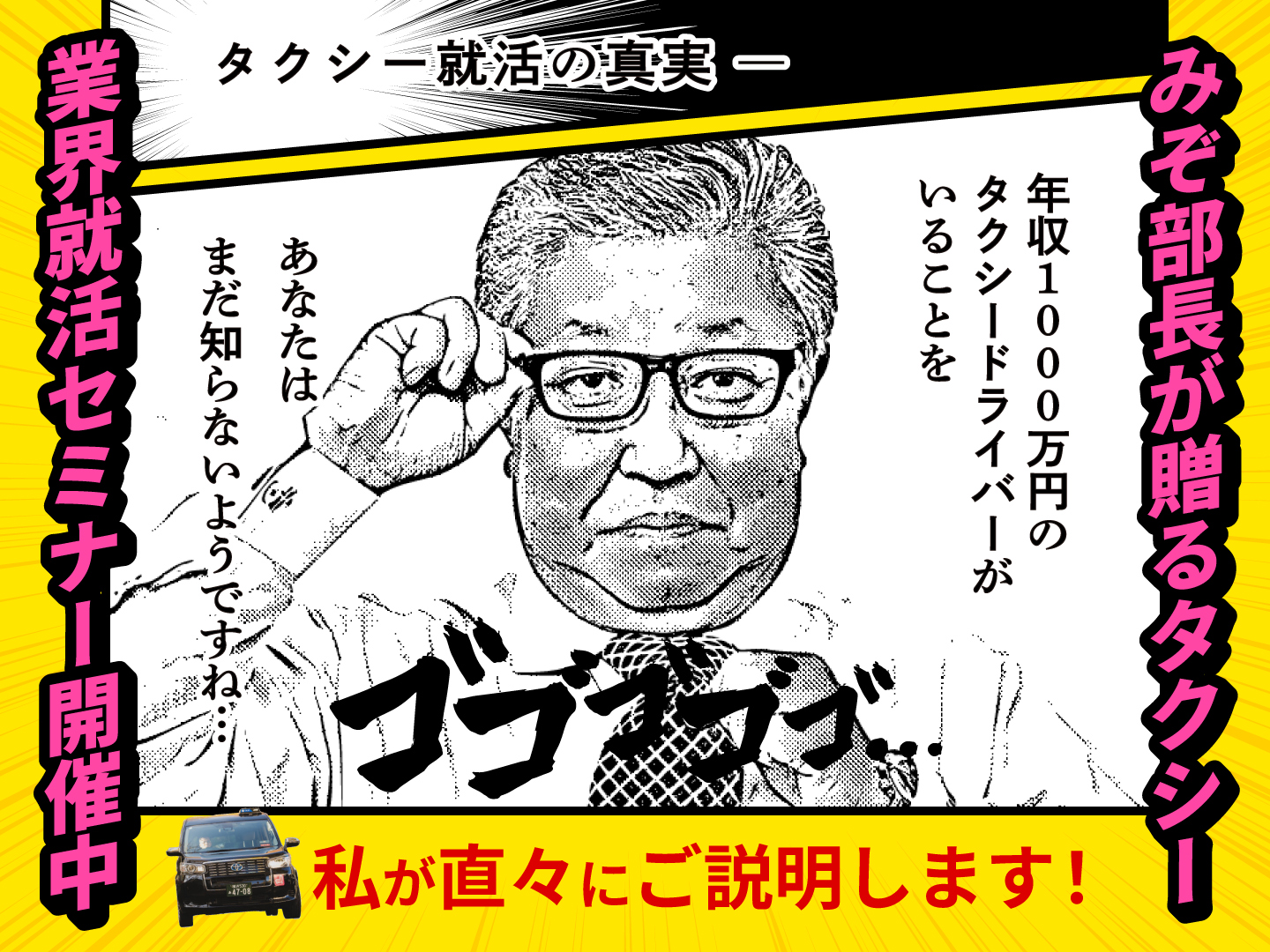業界のこと
【永久保存版】タクシー丸わかりガイド Vol.5 最新データでタクシー業界を紐解く!タクシーの「将来性」を解説。
「タクシー業界って、将来性あるの?」
そんな疑問を持っている方にこそ読んでほしいのが、
今回の“将来性編”。高齢化、インバウンド増加、若者の車離れ…。
社会の変化とともに、実はタクシーのニーズは今も確実に広がっています。
一方で、ドライバー不足やコスト増、ライドシェアの登場など、
課題も少なくありません。
それでもなおタクシー業界が「安定」と「成長」の両方を見込めるのは、
公共交通インフラとしての立ち位置と、変化に対応する柔軟な体制があるからこそ。
本記事では、最新データや現場のリアルな実情をもとに、
タクシー業界の未来を多角的に解説。
キャリアとしての安定性や、進化し続ける可能性を、わかりやすくお伝えします。
CONTENTS
こんな方にオススメ!
- タクシー業界の未来に興味がある人
- 今後のタクシー運転手の将来性を知りたい人
- 将来性のある仕事を探している人
1.データで読み解く、タクシー業界の現在地と未来図

1-1.高齢化社会で「移動インフラ」としての重要性が増加
いま、日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。
総務省「統計からみた我が国の高齢者(2024年)」によると、
2024年の65歳以上の高齢者人口は3,625万人と過去最多を更新。
総人口に占める割合(高齢化率)は29.3%に達しています。
これは日本人の約3人に1人が高齢者という計算です。
1950年には4.9%、2005年で20%だったことを考えると、
その増加スピードがいかに急激かがわかります。
また、内閣府「令和6年版高齢社会白書」によれば、
都市部に限らず地方では高齢化の割合がさらに深刻で、
2045年には40%を超える地域が多くなるという推計も示されています。
こうした中で、高齢者の移動をどう支えるかは、
交通政策や地域社会にとって大きな課題となっています。
バスや電車などの公共交通が縮小・撤退する地域が増えるなかで、
「身近に呼べる移動手段」としてタクシーが担う役割は確実に大きくなっています。
実際、買い物や通院といった日常生活を支える移動手段として、
タクシーは高齢者にとって欠かせない存在となりつつあります。
これからも、高齢化は止まりません。
だからこそ、タクシー業界は「地域社会のインフラ」としての使命を帯びながら、
安定した需要が見込まれる分野なのです。
※出典:総務省統計局「統計トピックスNo.142 統計からみた我が国の高齢者」
URL:https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf
※出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書」
URL:https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf
※今後も需要が見込める4つの理由が知りたい方はこちら
1-2.インバウンド観光がタクシー業界の追い風に
訪日外国人観光客(インバウンド)は、2024年に約3687万人で過去最高を記録。
2030年には6000万人の目標も掲げられるなど、
タクシー業界にとっても重要な追い風となっています。
日本政府観光局(JNTO)の統計によると、
2025年6月の訪日外客数は中国が約79万人で最多。
続いて韓国(約73万人)、台湾(約58万人)と、
東アジアを中心に多くの観光客が日本を訪れているため、
語学力のあるドライバー需要も高まっています。
また、観光庁の「インバウンド消費動向調査」では、
都市部だけでなく地方エリアへの訪問が増加しており、
移動手段としてハイヤー・タクシーの需要も拡大しています。
とくに家族連れや高齢の旅行者、荷物の多い観光客にとって、
ドア・ツー・ドアで移動できるタクシーは非常に利便性の高い移動手段です。
今後は多言語対応・キャッシュレス決済・
観光知識を備えたドライバーのニーズも増していくと考えられ、
インバウンド対応力はタクシー会社にとって重要な競争力となっていきます。
訪日客の増加は、一時的なブームではなく、
タクシーの新たな利用層の拡大という意味でも、
将来性を支える大きな柱になりつつあります。
※出典:観光庁「インバウンド消費動向調査」
URL: https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html
出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客統計」
URL: https://www.jnto.go.jp/statistics/data/visitors-statistics/
※タクシー業界の今と未来をこちらで徹底解説しています
1-3.車離れとDXが生んだ“新しいタクシー需要”
ここ数年、タクシー業界の需要層に大きな変化が起きています。
その背景にあるのが、若年層の「車離れ」と、
DX(デジタルトランスフォーメーション)による利便性の向上です。
KINTOが2025年に行った調査では、
都内のZ世代の約72.8%が「若者のクルマ離れ」を自覚していると回答し、
前年から20ポイント以上の急上昇を記録しました。
地方でも約半数が同様の意識を持っており、
若者が「車を持たない」という選択をする時代が到来しています。
また、20代の自動車保有率は40%未満に留まり、
特に都市部では
「自家用車よりもスマホで呼べるタクシーを利用する」傾向が強まっています。
そうした中、配車アプリの進化が若年層のニーズにマッチし、
タクシーを“オンデマンド型交通手段”として再定義する動きが広がっています。
アプリひとつでタクシーを呼び、目的地を入力し、キャッシュレスで決済まで完了する。
この手軽さは、運転免許を持たない層や車の管理を負担に感じる層にとって、
非常に魅力的です。
こうしたテクノロジーと社会変化が重なった結果、
タクシーは“持たない時代の移動手段”として新たな需要を獲得しています。
実際、都市部の営業収入は右肩上がりに回復しており、
「ハイヤー・タクシー年鑑2025」によると、
東京では2025年5月時点の法人タクシー営業収入が平成・令和を通じて過去最高を更新。
神奈川・埼玉でも過去最高とまではいかないものの、コロナ前の2019年5月と比較して、
神奈川は111%、埼玉は112%と大幅に上昇しています。
都市部を中心に、タクシーを利用するお客様が着実に増えているという事実は、
業界の将来性を裏づける重要な兆しと言えるでしょう。
※出典:KINTO「2025年版 若者のクルマ離れが急拡大?」
URL: https://corp.kinto-jp.com/news/detail/?id=press_20250311
※出典:国土交通省白書「自動車利用の動向」
URL: https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h24/hakusho/h25/html/n1232000.html
※出典:ハイヤー・タクシー年鑑2025
1-4.“なくなる仕事”ではなく進化する仕事としてのタクシー
「自動運転が進めば、タクシードライバーの仕事はなくなるのでは?」
という声もありますが、現在の技術・法制度・社会ニーズを踏まえると、
タクシーは“なくなる仕事”ではなく“進化する仕事”であると考えられています。
たとえば、自動運転の実用化が進む中でも、
日本の法制度では運転者が責任を持つ形が基本。
特にタクシーのように「不特定多数の人を安全に運ぶ」業務では、
万が一の対応・判断・接客が求められるため、人の役割は依然として大きいのです。
また、世界の巨大企業も、タクシー会社との連携やMaaS事業に参入しており、
むしろタクシー業界を基盤にした新しいサービスモデルが注目されています。
タクシーは移動手段にとどまらず、高齢者や観光客、
障がい者など多様なニーズに対応できる「多機能モビリティ」として
社会インフラ化が進んでいるのです。
さらにタクシーでは、AIには真似できない“人間力”が求められる場面も多数存在します。
目的地までの最短ルートを選ぶだけでなく、
「雨の日は入口付近で降ろしてあげる」「遠回りでも景色がいい道を選ぶ」
といった思いやりある判断は、タクシードライバーならではの価値です。
タクシー業界は技術革新とともに確実に変化していますが、
それは“人が不要になる”という意味ではありません。
人の価値を活かしながら進化する仕事として、
今後も社会に求められ続けていくでしょう。
2.タクシーが“安定している”と言える構造的な理由

2-1.国に認められた公共交通機関という立ち位置
タクシーは、鉄道やバスと同様に「公共交通機関」として
国から正式に認可を受けた事業です。
運賃や営業区域、車両数などが国土交通省の認可制で管理されているため、
安定した営業環境が守られています。
また、利用者からのニーズが一定以上見込める地域にしか新規許可が出ないため、
過当競争になりにくい点も特徴です。
三和交通のように、長年地域に根ざしてサービスを提供している会社にとっては、
この「国に守られている構造」が、
着実に信頼と収益を積み上げていく基盤となっています。
タクシーが“生活に必要なインフラ”とみなされているからこそ、
景気変動や社会情勢の影響を受けにくいのです。
※「タクシー業界は終わり?」気になるその答えはここに書いてあります
2-2.需要が途切れにくい“地域密着型”の収益構造
タクシーの強みは、地域に密着した「移動ニーズ」に応えるサービスであることです。
たとえば病院への通院、買い物、駅への送迎、飲食後の帰宅など、
日常生活の中に自然と溶け込んでいます。
これらは季節や景気に左右されにくく、
むしろ高齢化や車離れの影響で利用者は今後さらに増えていくと予測されています。
三和交通の営業エリアである東京・神奈川・埼玉では、
地域とのつながりを大切にしたサービスを積み重ねてきた結果、
地元での認知度も高く、多くのお客様から継続的に選ばれています。
リピーターの方が多いのも、地域に根ざした丁寧な接客の賜物。
まさに“暮らしに欠かせない足”として、日々の生活を支える存在となっています。
2-3.ライバルが増えない!業界特有の高い参入障壁
タクシー業界は「誰でも始められる」業界ではありません。
新規参入には国の認可が必要で、
営業区域・台数・料金体系なども細かく定められており、
事実上、大きな資本力や既存のノウハウがないと参入は困難です。
このような“参入障壁の高さ”が、安定した競争環境を守る防波堤となっています。
また、2024年に一部地域で始まった「日本版ライドシェア」も、
運行管理はタクシー会社が担う形式であり、
既存業者が排除されるような制度設計にはなっていません。
むしろ信頼あるタクシー会社が「新しい形での移動サービス」を
展開していく未来が期待されています。
※話題の「ライドシェア」について知りたい方は見てみてくださいね
3.タクシードライバーとして「働く上での将来性」

3-1.ドライバーから管理職・専門職へ。広がるキャリアの選択肢
かつては「ドライバーで終わり」というイメージもあったタクシー業界ですが、
現在では各社でキャリアステップが整備され、
長期的な視野で働ける環境が整いつつあります。
三和交通でも、現場での経験を生かしてステップアップしていく
キャリアパスが用意されています。
たとえば、営業所の管理を担う「運行管理者」や、配車を統括する「配車センター」、
車両整備を担う「整備工場職」、ガソリンや洗車を担当する「スタンド職員」など、
多彩な専門職があります。
また、本部で企画や人事に携わるポジションに進む道もあります。
実際に三和交通の各営業所長や役員は、すべてドライバー経験者。
現場を知るからこそできる判断が評価され、キャリアアップにつながっています。
年齢や性別に関係なく、一人ひとりの「頑張り」が形になる職場です。
こうしたキャリアの可能性を後押しするように、
近年ではタクシー業界に入る人自体が増加傾向にあります。
特に都市部ではドライバー数が回復基調にあり、
令和4年の全国214,972人から、令和5年には217,161人と2,189人の純増を記録
(全国的に13年ぶりにドライバー数が増加)。
東京・神奈川・大阪などを中心に、若手や女性の入職が着実に進んでいます
(ハイヤー・タクシー年鑑2025より)。
新卒採用もじわじわと増加しており、
「運転×接客」をキャリアとして選ぶ人が確実に増えていることが、
将来性の高さを物語っています。
※タクシードライバーに20代の若手が増えている理由をここから知ることができます
3-2.未経験からでも安定収入。年収1000万円も夢じゃない
タクシードライバーの魅力の一つは、
努力がそのまま収入に反映される仕組みにあります。
三和交通では【AB型賃金制度】を採用しており、
固定給+歩合給+賞与という安定性と成果報酬のバランスを実現。
営業努力や戦略次第で高収入も十分に狙えます。
実際に、年収600〜800万円クラスのドライバーは多数在籍しており、
トップクラスでは年収1000万円超という実例もあります。
さらに、給与保障や賞与制度、入社初期の研修支援など、
未経験者でも安心してスタートできる制度が充実しています。
「今より収入を上げたい」「自分のペースで稼ぎたい」という方にとって、
タクシーは実力勝負の世界でありながら、将来への安定感も兼ね備えた職種です。
※タクシードライバーで年収1000万円も夢じゃない?気になる方はこちらをどうぞ
3-3.プレミアムサービスという“未来型キャリア”
三和交通では、接客・安全・営業力など
複数の基準を満たしたドライバーだけが担当できる
「GO PREMIUM(ゴープレミアム)」というハイグレードサービスがあります。
これは通常のタクシーとは異なり、ワンランク上の接客と車両で、
特別な乗車体験を提供するサービスです。
GO PREMIUMドライバーは、指名やリピート率が高く、配車単価も高いため、
収入面でも大きなアドバンテージがあります。
また「質の高い接客が求められる」という点では、
ホテル業界や航空業界と同様、
サービス業としてのやりがいも感じられるポジションです。
このように、ただ「走るだけ」で終わらないキャリアがあるのも、
現代のタクシー業界の大きな変化の一つ。
専門性やホスピタリティを磨けば、
より高度なステージへと進んでいける環境が整っています。
※GO PREMIUM専属ドライバーという働き方を解説しています
4.まとめ
いかがでしたか?
高齢化やインバウンド需要の増加、配車アプリの普及など、
タクシー業界は今なお成長のチャンスにあふれています。
実際、東京をはじめとする都市部では、
営業収入や乗車回数がコロナ前を超えて回復しつつあり、
ドライバー数も若手や女性を中心に増加傾向にあります。
タクシーは、今まさに“必要とされている”職業なのです。
そんな中、三和交通では、安心の研修体制やキャリアアップの仕組み、
GO PREMIUMなどの高品質サービスを通じて、
未経験者でも長く活躍できる環境を整えています。
「将来に不安がある」「手に職をつけたい」そんな方にとって、
タクシーという選択肢は、今あらためて現実的で価値あるものになっています。
少しでも興味を感じた方は、
ぜひお気軽に三和交通までお問い合わせください。